
動物を愛し、ドクタードリトルのモデルとも言われるジョンハンター。世界中の珍獣をコレクションにもち、世界中の民族や奇形の人も標本としてコレクションしていた奇人です。
彼のコレクションは現在もハンテリアン博物館に貯蔵されています。

墓堀りの首謀者、解剖医、外科医、博物学者と様々な顔を持ち、死後『科学的外科の創始者』といわれるまでになります。弟子には天然痘ワクチンを開発したエドワード・ジェンナーをもちます。
数々の実験を中心に、時代背景、考え方、周囲のいざこざをふんだんに盛り込みながら、鬼才ジョン・ハンターの生涯を綴った本です。
概要
時代背景
18世紀半ばのロンドン。
日本では江戸幕府第9代征夷大将軍、徳川家重の時代。日本史に疎い私からすると、特に歴史的な印象が薄い時代(教養のなさを露呈)。 杉田玄白が解体新書の翻訳を始めたのが、1771年、1774年発刊。その少し前の話。
当時のロンドンでは、 医者といえば内科医のことを指し、外科(といえるほどではないが)は床屋が兼任していた。床屋の前にある赤白のポールは、赤は血を、白は包帯を表しているのは有名な話だ。

床屋ではイボ切除、排膿、瀉血が行われていた。 高貴な職業である医者は自ら手を汚すことを嫌い、このような処置を避けた。
当時ロンドンの平均寿命は37歳。
子供の死亡率は高く、ジフテリア、はしか、おたふく、しょ紅熱、インフルエンザ、結核から逃れなければならない。刑務所や病院、船では天然痘や発疹チフスが流行った。抗生物質や消毒液、麻酔はない。
医者や学者は口では科学の進歩を唱えながらも、現実は紀元前古代ギリシャでヒポクラテスが唱えた4液説「あらゆる病気は、血液、粘液、黒胆汁、黄胆汁の4つの体液の不均衡によるものである」にしがみついた医療から抜け出せずにいた。
医療がうさんくさいものなので、根拠のない民間療法を試すことが日常化していた。 胃腸洗浄のための嘔吐剤や下剤、気を失うまで血を抜く、有害物質でできた薬、水銀、アヘン…。 今となっては医療とはいえないものしかなかったロンドンでは、医者のたまごたちが解剖学を目で見て学ぶ機会がほとんどなかった。
そんな時代に毎日のように解剖教室を開き、多くの熱心な若者たちを集めたのがウィリアム・ハンターであった。後にその解剖教室を任されることになったのが弟のジョン・ハンターである。
解剖検体の確保
毎日のように開かれる解剖教室のため、多数の検体を確保しなければならない。 すでに医者としての地位を確保しつつあった兄ウィリアムに死体の確保を依頼されたジョン・ハンターは墓掘りによって、遺体を確保する。

自らも墓掘りをしたが、それだけではなく、いわゆる闇の組織とのつながりをもち、ありとあらゆる方法で死体の確保に努めた。 正常な臓器組織を観察するため、死後の変化が可能な限り少ない死亡直後、その上健康な人の遺体でなければならない。代表的なものは絞首刑にされた囚人である。
宗教上、死後遺体をバラバラにされると、最後の審判の日に復活できないと考えられていて、本人と遺族は遺体が解剖医に渡ることを嫌った。さらに当時の絞首刑は、ゆっくりした窒息死を目的としていたため、囚人が死にきれないこともあった。解剖されている間に意識が戻る最悪のケースもあったので、そういう意味でも解剖医に渡ることを恐れた。
絞首刑執行直後の遺体は遺族とジョンたちで取り合った。
葬儀屋を買収して、棺の中身を石にすり替えることもやられた。
解剖医や外科医に雇われた人のなかには、死体確保のための殺人まで行われていた。
ジョンの研究
生物に関する知的好奇心が特に高く、生涯多くの実験、観察により様々な研究を進めた。
- トカゲの尻尾の再生
- 鶏卵の発生過程
- 歯の移植
- 雌鶏への睾丸移植
- アキレス腱の自然治癒過程
- デンキウナギの放電
- 奇形のコレクション
- 淋病と梅毒
これらはすべてこの本で紹介されている例だが、一部にすぎない。
特に有名なのは性病の研究だろう。他人を実験体にできないからと、自らで実験を行った。
淋病患者の性器の膿を使用して、自ら感染した。淋病を無治療で放置し、悪化すると梅毒になるという仮説を検証したのだ。その患者が淋病と梅毒両方に感染している可能性を完全に見落としていたのは、彼のチャーミングな部分だろう(チャーミングで済ますな)。抗生物質はないため、生涯性病に悩むことになったのだが。
動物を使う実験も多く、ドリトル先生のモデルになったとも言われる。動物を飼い、患者のように丁寧に扱い、ロンドン獣医大学の設立に貢献している。
外科医ジョン・ハンター
卓越したメス捌きと観察力によりメキメキと解剖の才能を発揮したジョン・ハンターは兄の推薦で外科医の道を進む。優秀な解剖医は優秀な外科医となる。
その時代の定説を覆す治療を次々に提唱、実現していく。実験や観察に意欲的な一方で、なんでもかんでも切ればいいという安直な考えはなかった。不必要な外科的処置はやらないこと、観察と実験、科学的証拠を常に心掛けていた。
大昔からの伝統と他の外科医の嫉妬などにより所属病院内では生涯浮いた存在だった。しかし、病院の外ではその科学的手法は確実に広まっていた。これが後に「科学的外科の創始者」と呼ばれたジョン・ハンターの生涯だった。
考察
裏社会とつながり、周囲に批判されながらも独自の信念を貫いたジョン・ハンターは、世の中の常識をひっくり返し続け、現代外科の基礎を築きました。
現代の私たちがこの本を読むと、彼の考えに納得し、彼の邪魔をする周囲を批判したくなります。しかし、当時の彼は世間的には異端児で、笑いもので、理解しがたい男だったのでしょう。
確かに、墓堀りをはじめとした黒に近いグレーなことをやっていました。しかし、結果的に科学的外科の発展に必要不可欠であったことは、明解です。
いつの時代も新しいことには批判が集まります。特に情報社会の現代は、少しでも疑わしいことは、民意という「素人の」意見によって徹底的に潰されてしまいます。
批判を浴びながら挑戦し続けなければ革命は起こらないのかもしれません。「戦争は技術を進歩させる」ような皮肉的な面があるのは事実です。
ジョン・ハンターは数々の動物実験をやっていました。動物福祉の考慮から、動物実験の実施が慎重に検討される現代では、とてもとてもできないような実験の数々です(人の断脚すら無麻酔でやっていた時代ですけどね)。確かに動物にも人と同様に感情や痛みがあるとわかってきた今、動物福祉の尊重は必須です。しかし、その主張が必要以上に大きくなることは、科学の進歩のブレーキになるでしょう。
動物福祉尊重!動物実験反対!!と叫ぶ前に一度立ち止まってみてください。周囲の意見や世間の論調に惑わされず、これまでの動物実験による成果や我々が受けている恩恵を見直してみてもいいのではないでしょうか。
彼は安易な実験を繰り返してきたわけではありません。仮設、実験、検証をすべて記録して繰り返してきました。これは医学会だけでなく、科学の基礎そのものにも通ずると思います。手術自体も実施に常に慎重で、当時当たり前だった「掛け要素の強い」手術は避けるべきと教えています。
そこには自分の興味関心よりも命を尊重する姿勢が汲み取れます。実験者の在るべき姿、全科学者が学ぶべき姿勢を18世紀にすでに示してくれており、これはいつの時代の実験者、科学者も忘れてはならないものだと思います。

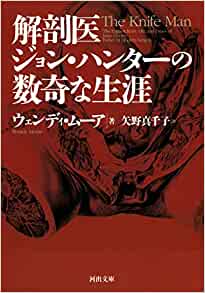
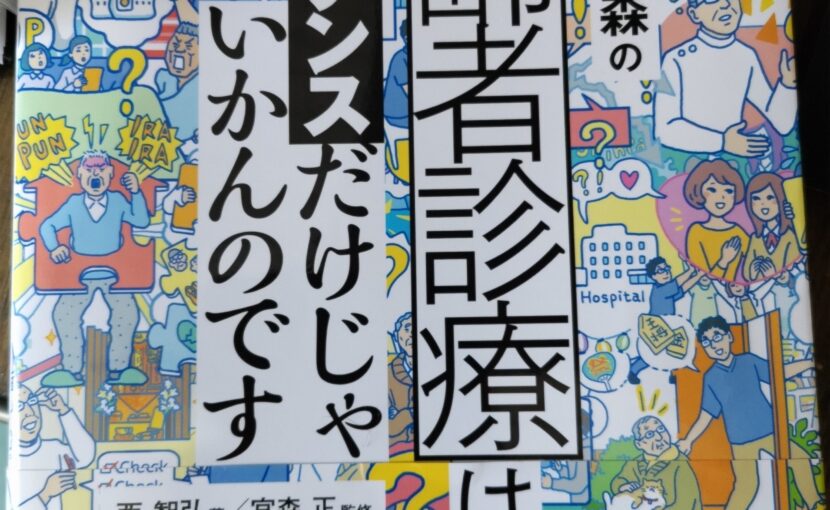
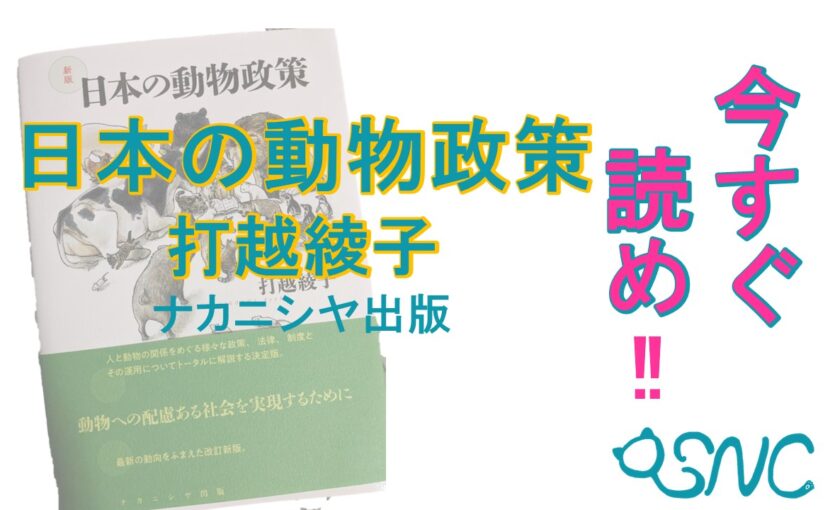

この記事へのコメントはありません。