動物保護界隈で、ミイラ取りがミイラになることは少なくない事例です。
今回は、保護犬、保護猫に関するミイラ取りがミイラになる『ミイラ案件』を解説します。
『ミイラ案件』とは
結論から言うと
動物の保護活動を続けた結果、自分のキャパシティを超える多頭飼育となり、最終的に保護者自身が支援される側になる状況
です。
保護している動物の数が増える中で、保護主の急な体調不良や死亡起こります。残された動物はあっという間に保護される側に転落します。
要は、保護活動家の多頭飼育崩壊をミイラ案件と呼んでいます。
この記事ではまず、「なぜミイラになるのか?」という原因とたどる経過を、次に保護活動を応援したい動物好きの方が知っておくべき「ミイラ予備軍」の特徴と見抜き方を解説し、最後に保護活動者へのメッセージをお伝えします。
なぜミイラ案件は後を絶たないのか
保護活動にハマる
目の前でかわいそうな動物がいると放っておけない。そんな気持ちから保護活動に尽力する方がほとんどかと思います。
勿論これはいうまでもなく、称賛に値する活動です。みなさん最初は単純に優しい心で1,2匹から始まります。
動物を救ったという何事にも代えがたい達成感があり、他人に感謝され承認欲求も満たされます。
さらに、SNSで発信すれば
「救ってくれてありがとう!」
「あなたがいなければ、この子はどうなっていたの…」
「こういう人がいるならまだまだ捨てたものじゃない」
などと応援メッセージが集まります。
こうして保護活動にハマります。
期待と使命感が追い打ちに
積極的に保護活動をしていることが周辺地域に知れ渡ると、「あの人にいえばなんとかしてくれる」という噂が広まります。
ここまで来ると、もう断れない。
期待に応えなければならないから。私が断ったらその犬や猫がどうなるのか心配で仕方がないから。断ったら私の存在意義がわからなくなるから。
さらにAmazonの「ほしい物リスト」や、寄付口座に支援が集まると、「これがあれば続けられる」「自分は評価されている」と思い込み、無理を使命感にすり替えてしまうのです。
ミイラ予備軍
私がやる、他の人ではできない等という思いから、誰にも頼ることができなくなるといよいよミイラ化は目前です。
保護依頼を断れず、いざというときにヘルプの声を上げることにも抵抗を感じるようになります。
ここでいうヘルプの声とは「寄付ください!」の声ではありませんからね。これはヘルプではなく、自己アピールの声です。
ヘルプの声とは、「もう限界だから最後終わらせるために助けて」という訴えです。
ミイラ予備軍はむしろ寄付を募る声は大きく、自分の保護動物を減らすための声はほぼ挙げません。
ここまで来ると、いつミイラになってもおかしくない状況といえます。
実はこの段階の人は多いです。
あなたが頼ったことある人やSNSなどで応援コメントを送ったことがある人も、もしかしたらミイラ予備軍かもしれません。
個人の限界とは
個人で管理できる能力はそれぞれ。
確かにそうなのですが、一般的に一人で管理できる数は法令により数値が出ています。詳しくはこちらから。
「あの人は動物の扱いに慣れているからそれ以上の数がいても大丈夫なんだ。」
ということはほぼあり得ません。経験豊富な保護者ほど、自らのキャパを意識して活動しています。
更に、個別管理、ペット飼育の知識と経験で群管理(シェルター管理)はできません。何年も猫の飼育経験があったとしても、シェルター管理は素人です。
ミイラ予備軍の特徴
ミイラ予備軍は4つの傾向が見られます。この特徴を把握することで、予備軍を見抜くことができます。
- 個人またはワンマン活動
- シェルターが汚い
- 連絡が遅い
- 寄付に依存・収支不明瞭
ミイラ予備軍を見抜かず応援してしまうと、間接的に動物虐待に加担することになりかねません。動物を守りたい、動物保護活動を応援したいと願う人は、ぜひ一度チェックしてみてください。
個人またはワンマン活動
ヘルプの声をあげられないのは、孤立した個人活動家に多い傾向です。外部に協力者がおらず孤立した活動の場合、ヘルプできませんし、歯止めがかからなくなります。
団体でも実質は代表のワンマン経営で、他のメンバーの意見が通らない場合は同様のリスクを抱えています。
個人でも団体でも、外に協力者がいるほうが健全ですね。
シェルターが汚い
一人で管理できる上限(法令基準以上は論外)を超えると、環境はすぐに悪化します。施設が汚いと感じたら、すでにキャパオーバーです。
それが3匹だとしても。
連絡が遅い
レスが早いのは仕事ができる人の特徴です。なんてビジネス書的な話をする気はありませんが、即時対応が必要な状況で何日も連絡がつかないのは異常です。
対応しきれていない証明にほかなりません。
なんでもかんでも無意味な相談をしてくる人が多く、そのような相談は後回しやスルーすることはありますよ?優先順位はあります。なので、連絡する側に問題があるケースもあります。
しかし「連絡するから」といっていつまでも連絡がないような保護活動家は、すでにキャパオーバーの可能性が高いです。
寄付依存・収支不明瞭
ほとんどの保護活動は寄付でなりたつボランティア活動です。
ただ、寄付が減るとすぐにあっぷあっぷしてしまう運営はいつミイラになってもおかしくないです。
特定NPOなどの法人でない限り収支報告は義務ではありませんが、そもそも収支が管理できていない活動はとてもハイリスク&動物の管理もずぶずぶなのではないかと疑ってしまいます。疑ったほうがいいです。
外部から確認できませんが、質問されても数字が曖昧な活動は信頼できませんし、すでにミイラ予備軍になっている可能性が含まれます。
美談にするな
団体のミイラ化は頭数規模が大きく、ニュースに取り上げられるなど衝撃も大きいです。内部告発などで判明するケースもあり、世間から大いに叩かれます。
一方で個人の活動家は、
「動物に優しい方があんなに頑張っていた。なのに、周囲は助けなかった」
と美談にされがちです。同じ動物の不適正飼養(ほとんどが虐待にあたる)をやっているにも関わらず。
いきすぎた保護活動を『美談』にしてしまうと、また同じことが違う場所で起こるだけです。ミイラ取りになるミイラを増やすだけなのです。
依頼者責任と保護主責任
保護を依頼する側も無責任という面はあります。丸投げは腹が立ちますよね。
ミイラ化しない活動家は、必ず依頼者にも仕事と責任を与えます。例えば
- 指定日に連れてくる(指定日まで連れてこさせない)
- 初期医療は済ませてから
- 一部費用を負担させる
こうすることで依頼主に一定の責任を負ってもらうことができます。
要は、依頼者の責任は保護活動者が設定できるのです。
保護したらそれはもう保護主の責任です。依頼者の丸投げを後から文句を言うような保護活動はすべきではありません。
依頼者さんがここまでやってくれたから、あとはこっちも頑張ろう!と気持ちよく活動したいものです。
とはいえ愚痴はなくなりませんけどねw
まとめ
動物を救いたいという善意から始まる保護活動が、いつの間にか自分自身や動物を苦しめる事態になる。それが「ミイラ案件」です。
どんなに立派な理念があっても、管理能力を超えれば、それはただの「不適正飼養」です。
保護活動に関わるすべての人が、冷静な視点と適切な距離感を持って関わっていくことが、動物たちの本当の幸せにつながります。
もしここまで読んでいただいた方の中に、自分はもうヘルプの声をあげる時かもしれないと思う方がいたならば、「ブログ見ました」と、こっそり相談ください。協力させていただきます。
ブログ見ましたと添えていただけないと、ふざけんな自己責任でやれと突き放してしまうかもしれませんのでw必ず伝えてください。
よろしくお願いいたします。

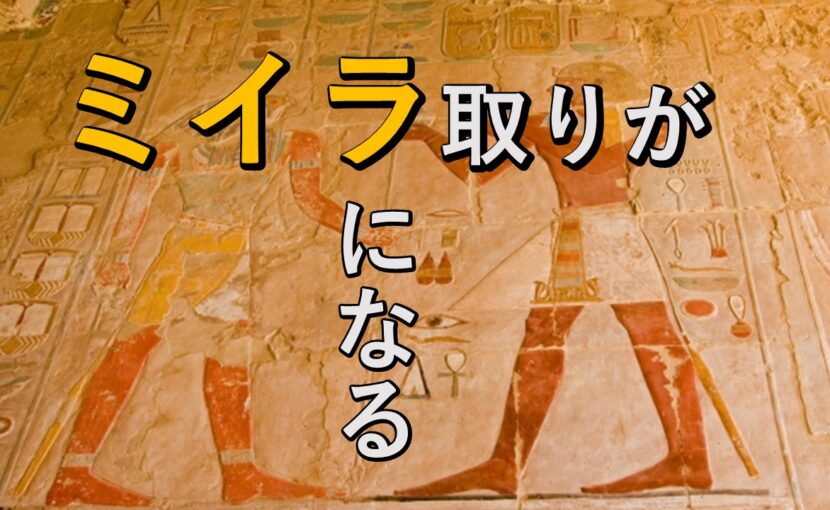
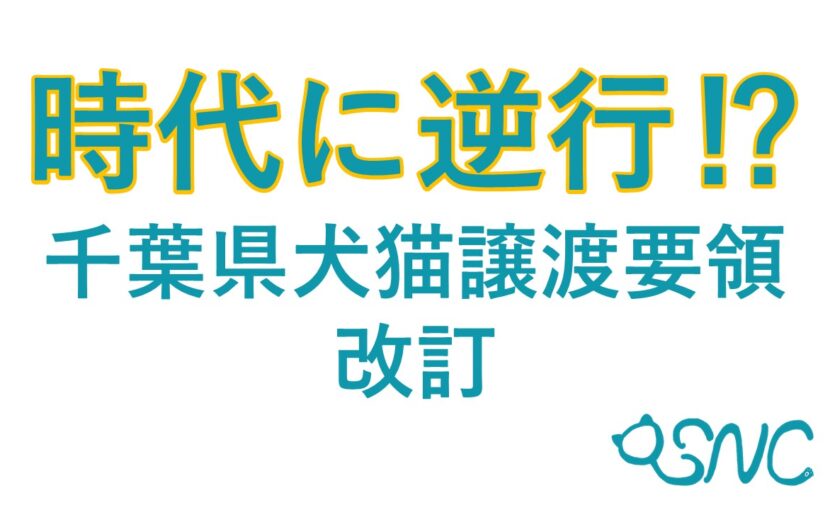

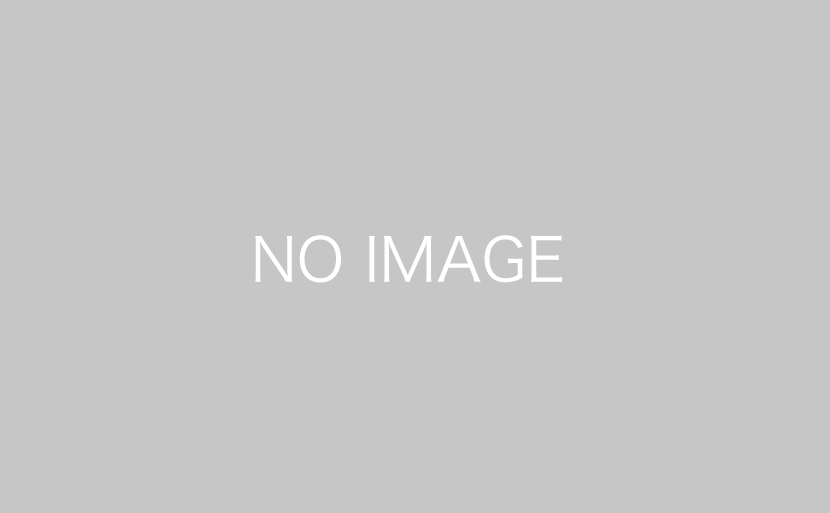


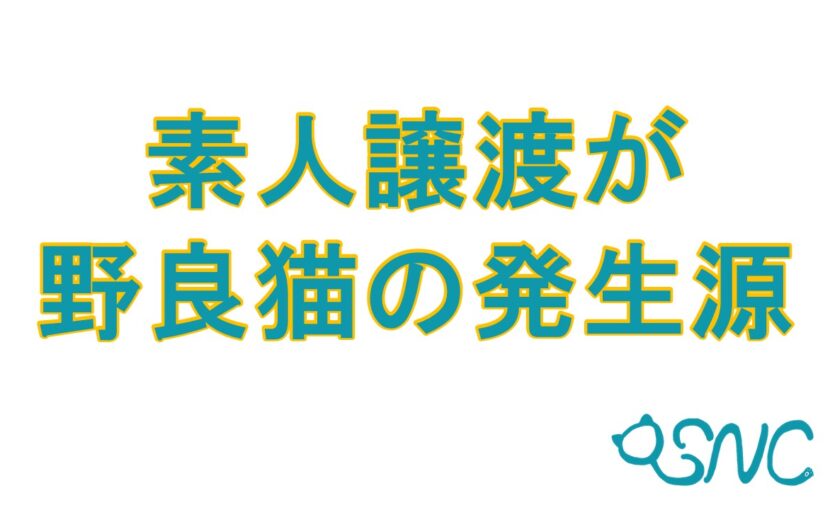
この記事へのコメントはありません。