今治市の猫保護団体の代表が自殺という衝撃的なニュースが入ってきました。
まずは代表の方のお悔やみを申し上げます。
結果、猫も70匹ほど取り残されたとのことです。
まさにミイラ取りがミイラになる案件。
同様の事件が二度と起こって欲しくないと思い、記事にします。
※センシティブな内容であるため、ここでは一切記事リンクは貼りません。
ミイラ案件自体の問題点は以前の記事のまとめてありますので、今回は少し違った視点から。
当該団体の実態
まずはことの概要を。
私は全く知らない団体ですので、あくまでネット上で集めた情報(発信元が当該団体のもの中心)をまとめます。
事実と異なる可能性があることはあらかじめご了承ください。
- 2023年10月 団体立ち上げ
- 活動の中心はTNRで保護は原則保護主負担
- 2023年12月 クラウドファンディングで157万円(目標300万円)集める
- この時点で80匹保護、20匹譲渡
- シェルターはボロボロ
- 2025年4月 代表自死
TNR中心のはずなのに
当該団体は綺麗なHPがありました。
そこにはっきりと記載してあります。
当団体では、地域猫のTNRを主に保護活動しております。そのため成猫・子猫を保護した場合、基本的には保護主さまで養育していただくようお願いしております。当団体では里親探し(保護猫として当団体SNSに掲載、保護猫を譲渡会に参加させる等)のご協力をいたします。
団体の立ち上げ当初は、保護しきれないことを理解していたのだと思います。
愛媛県今治市というまだまだ野良猫が多い地域で活動をする場合、それが妥当だと私も思います。
しかし、いつの間にか年間80以上の猫を保護してしまいました。
にも関わらず、20匹程度しか譲渡できていません。
つまり、単純計算で毎月5匹も猫が増え続けたのです。
明らかに多頭飼育崩壊待ったなしです。
応援者の責任
クラウドファンディングには以下の文言が赤字で記載されていました。
このプロジェクトの成功が無ければ 来年以降の活動が出来ません
300万円欲しかったのに半額しか集まらなかったのであれば、本当にやめるべきでした。300万円なければ続けられないと本当に思っていたなら、その時点では正常な判断ができていたと思います。
単に資金集めのための煽り文句かもしれません。
とはいえ詐欺師でない限り継続困難だからクラウドファンディングを立ち上げているのは間違いありません。
クラウドファンディングは応援コメントを書いてもらうことがあります。
しかし、クラウドファンディング失敗後、応援者たちが応援し続けているのは無責任だと考えます。
目標金額が集まらなければ継続困難だと誰が見ても明らかで、本人は助けを求めていて、その助けが足りなかった(クラウドファンディング失敗)にも関わらず、活動継続を応援し続けられたら、辞めるわけにはいかない状況になります。
世の中にある「紹介」や「応援」って、もっと責任持ってやるべきことだと私は思っています。
とはいえ、保護活動をやめるのはとても難しいことだというのは十分承知しています。
今いる動物の行き先を決めるのに時間も費用もかかります。伝手も必要かもしれません。
自分が保護活動から引退して、すべての動物の行き先を決めるのは困難を極めます。
例えば当該団体のクラウドファンディングが、保護を辞めるための資金であれば、私も支援を検討する価値があったと思います。
一部で問題視されている保護団体のクラウドファンディングの共通項のひとつは「終わりが見えない」ことですので。
行政の役割
行政がどれだけ指導に入っていたか?活動を辞めることを促さなかったのか?はわかりませんが、とても重要なポイントだととらえています。
当該団体の活動は第二種動物取扱業に該当します。
飼養管理基準が設けられていますが、クラウドファンディングに掲載の写真を見る限り、飼養施設がそれを満たしていたとは考えづらい飼育環境です。
更に「一人あたり30匹まで」という頭数制限もありますが、最終的には代表一人で70匹近くを世話していたという情報もあり、本当ならば違法です。
10名ほどのスタッフがいたとありますが、実際には支援が得られていなかった可能性があります。離れていったのか、名前だけ貸したのか、幽霊部員だったか。
そのあたりについて行政指導がどれだけ入っていたかが気になるところです。
全く指導していなかったことはさすがにないと思いますが、こんな悲劇を抑止するための行政機関が、それを止められなかったことは反省すべきです。
人ひとりの命が失われたのです。
動物を守るだけが動物愛護管理行政の役割ではありません。
本人の自己責任であることは間違いありませんが、まさに動物を救うことで人も救うことができるケースだったと思います。
(万が一、厳しい指導が入っていて、それにも耐えられなくなった代表がこのような結果を選んでしまったのであれば、話はまた別になってしまうのですが。)
更にいうと、ここまでのケースであれば本来は活動を辞めるように促すべきです。
行政には、飼育環境の改善だけでなく、活動の「終了」も選択肢に含めた助言が必要です。例えば
「動物取扱業者からの引き取りは原則できませんが、このまま続けていたら動物もあなたも苦しくなって共倒れになるのは明らかです。活動から足を洗うなら、引き取ります。」といって行政が引き取る提案をする等。
保護活動者が、限界です助けてくださいと助けを求めたとき、うちは引き取りませんと突っぱねる一辺倒な対応はあってはならないと思います。
だから、殺処分ゼロは反対なのです。
それを拒んでいるのは、現状の「動物愛護世論」なのですが。
行政にも責任がある!行政がちゃんとやっていれば抑止できた!とまでは到底言えません。ただ、このまま殺処分ゼロのみを正義とする行政対応では、同じ悲劇を繰り返します。
行政は、最期の砦であるべきです。
最後に
私たちはこの悲劇から学ばなければなりません。
応援する者も、見守る者も、そして行政も、「保護活動の限界」をもっと理解し、現実的にできる活動を推奨する必要があります。
当院ではこのような悲劇を起こさないために、官民連携で問題解決にあたっています。お気軽に相談ください。

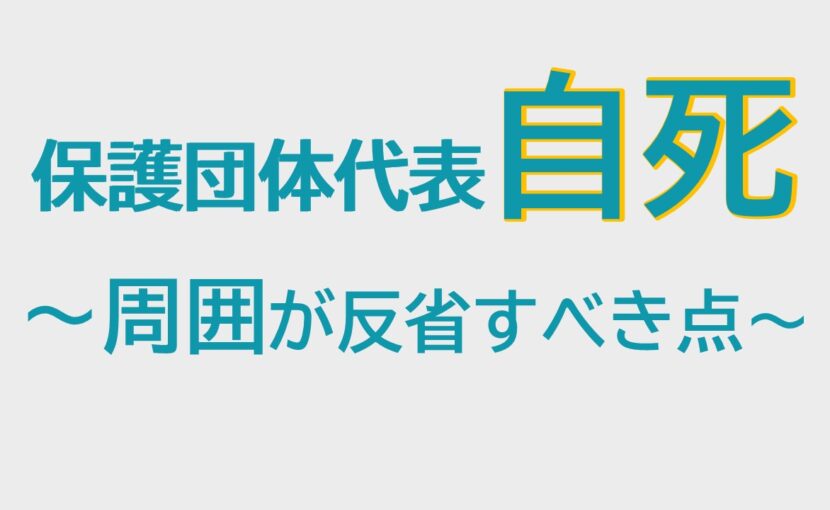
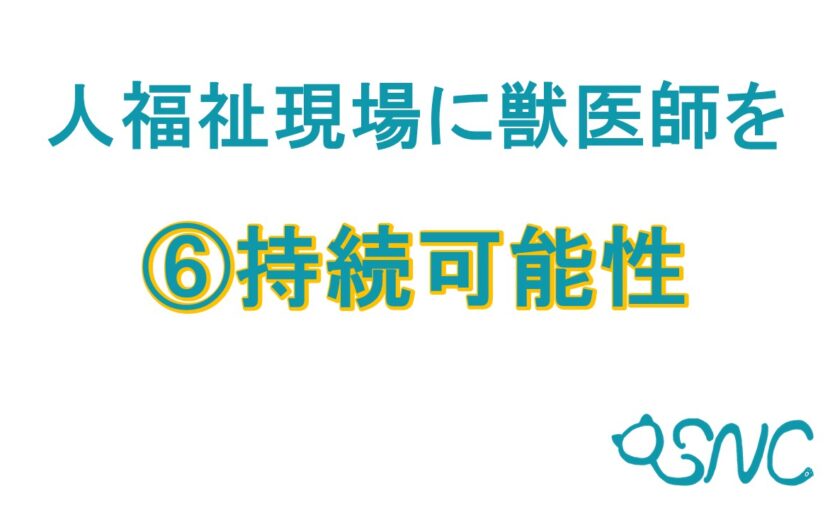
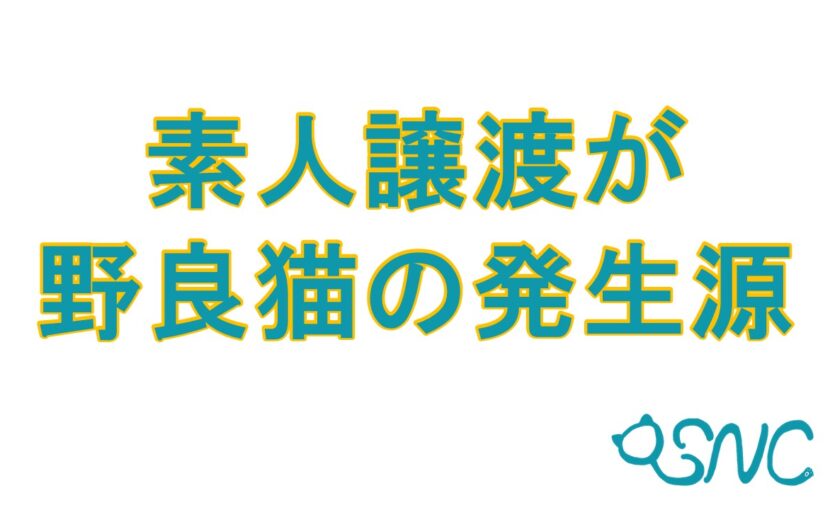
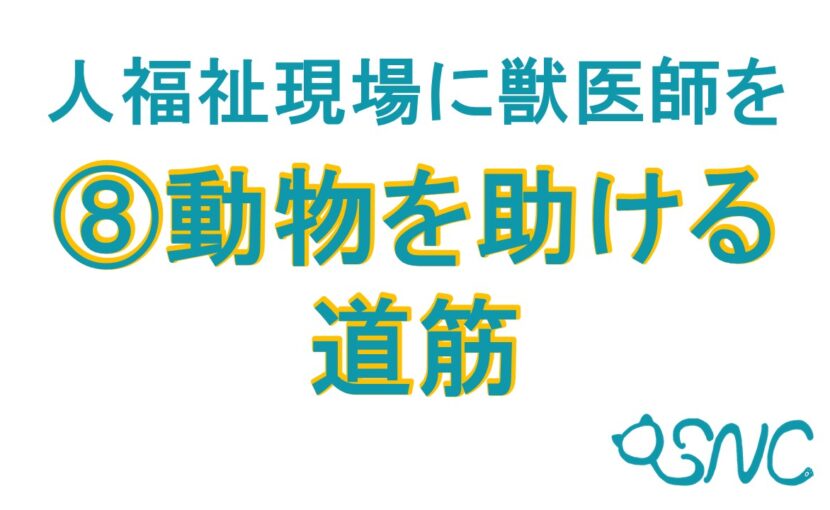
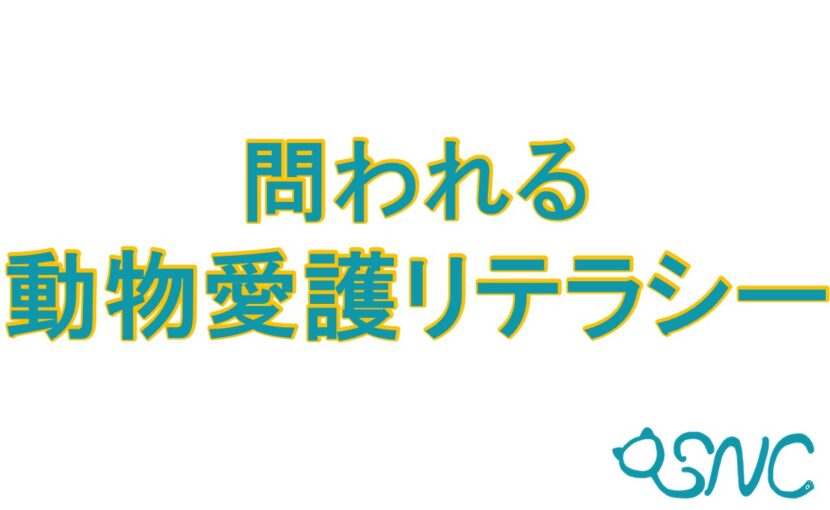

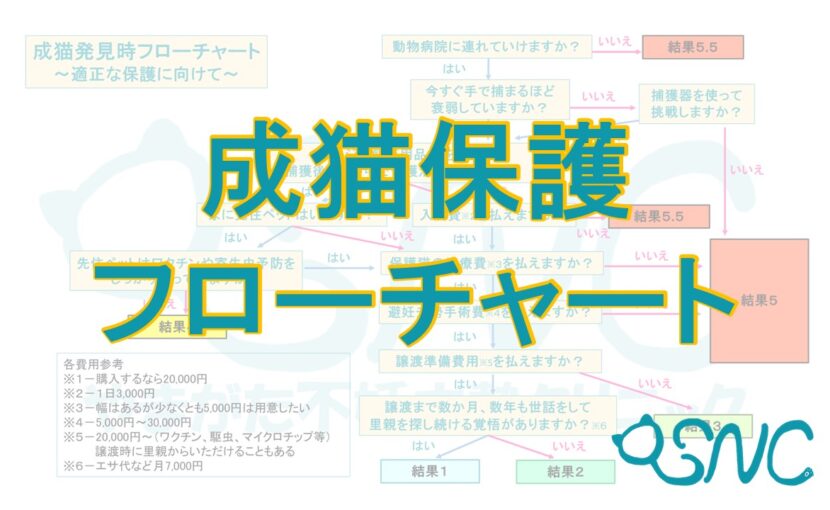
失礼します。
代表と知り合いだったものです。活動には関わっていない知り合いです。とても明るい活動的な方でいつも動物病院でお会いしていました。ケージやネコ砂やエサが足りないと話しておられました。
行政は何もしてないはずです。「市役所から野良猫を保護して欲しいと連絡があったから行ってくるわ」とご本人から聞いた事があります。
行政は保護猫団体を頼りにしていた印象を受けました。
当時、何も出来なかったことを悔いています。
松山でTNRを得意とする団体と懇意にしていたため、
TNR現場の保護対象となった猫を引き受けざるを得ない状況があったようです。
代表が逝去した後、
その松山の団体さんが現場へ駆け付け、
責任を果たそうとしていた姿勢は立派だと感じます。
一方で、限界を超える前に立ち止まる判断はできなかったのだろうかという思いも残ります。