前回の『優秀な行政職員』の記事は読んでいただけたでしょうか。
市民から行政に出てくるご意見、時には議員さんを使って通そうとしてくる要望に対して、行政職員はプロとして本当にそれは市のためになるか?を考える必要があります。
案を通せるか?の前に、それができたら市や市民の利益となるか?を考えます。これができるのが優秀な行政職員だと考えます。
周りを観る行政
利益となるか検討する際、それがその市にとって新しい取り組みの場合は特に、他の行政で同じような施策をやっているかを調べます。
同様の施策に取り組んでいる自治体があると、横に倣えで取り組みやすいです。
逆に、一番乗り!全国初!が好きな積極的な職員さんもいますが、稀です。
(実はとある市で、やまがたを顧問にする予算を請求してくれた職員さんがいましたが、予算とおらずでした。残念。まだ全国初の席、残ってますので是非w)
他の自治体が同様の施策に取り組んでいればマネできるという行政の性格は皆さんご存知のとおりです。
「他に例がない」「有用な施策かわからないのでできない」等といって話が進まなかった経験は、何回もあると思います。
これは行政病なので、これがないほうが不思議なくらいです。
周りを観ていない行政
しかし、先行している自治体がどれほどの効果を出しているかまで観ているか?というと、そっちはあまりやらないです。
全く観てないことはないですよ。
ただ、他自治体の先行事例の効果測定まで追って、自分の自治体で同様の施策を施行した際の有用性を予測したり、有用性が乏しいと予測した場合、それを議会で答弁し、案を却下すること、つまりへぼい案を論理でねじ伏せることは稀です。
行政職員はプロとして施策の有効性を考える必要があると冒頭で述べました。
行政職員をプロというのは少し違和感がありますが(専門的な知識を持ち合わせていない事務職員がその席に就くことになるので)、公益性を担うという意味ではプロです。唯一無二のプロであるべきです。
その公益性を担うプロが、自分たちの業務を意味のあるものにできないのは、仕事とは呼べませんからね。
「行政ではないので厳正な審査をします」
なぜこんな話をしたのかというと、手術費用の助成について、
「行政による支援ではないので、厳正な審査があります」とのポストをXで見たからです。
民間の手術費用助成に携わっている団体さんのポストです。
このポストをした団体さんの管轄自治体がどのような施策をしているのか、真相はわかりません。
ただ、こう言われてしまうのはやはり残念です。
地域猫活動って意味あるの?
TNRって意味あるの?
手術代補助金出して、意味あるの?
それを職員が自問自答できるか人が優秀です。
他の自治体の同様の施策が、自分のところで意味のあるものにする場合、どのような条件にすればいい施策になるかを考えるべきです。
それを考え抜くと、ある程度「助成金を出すための条件」という名の「審査」が必要になってくるのが自然です。
例えば、野良猫対策として、去勢手術に補助金を出している自治体は多いです。その条件として設けているのは、せいぜい
「地域猫活動には、3名以上の人が必要」くらいではありませんか?
ご存じの通り、そんな条件をクリアしただけで地域猫活動はうまくいきません。結果、意味のない施策となります。
もっと緩いと、地域猫ではなくても、飼い主のいない猫なら出します。としている自治体も多いです。
背景には行政文化がある
とはいえ、条件を厳しくすればすべてOKかと言われると、行政ならではの困りごとがあります。
「せっかく用意した助成制度が誰にも使われないと、それは失敗施策。」
となってしまう。こうなると当然次年度に予算はつきません。
このバランスが行政の難しいところです。
だからこそ、他所の自治体の効果測定を調べてから立案しようということなのですが…
ただ、散々調べて挑戦してみたものの失敗となった施策は仕方なし!それでよし。としてほしいです。
そうでなければ、チャレンジする職員はいなくなります。失敗したなら、助成条件を変える等して再チャレンジできる文化が行政にあるといいなと個人的には思います。
でないと優秀な職員は退職し、これまでと同じ施策しかできず、行政サービスは停滞します。停滞は衰退です。
こんな行政文化になってしまったのも、過剰な行政批判が原因かもしれませんが。

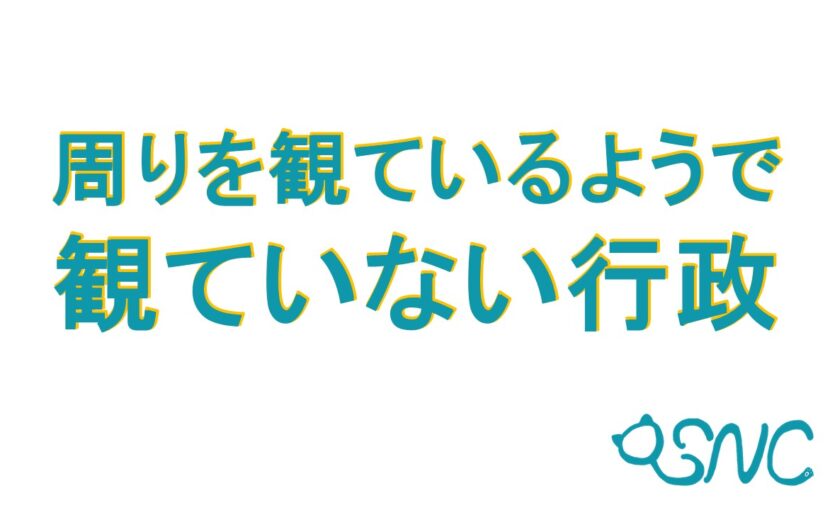
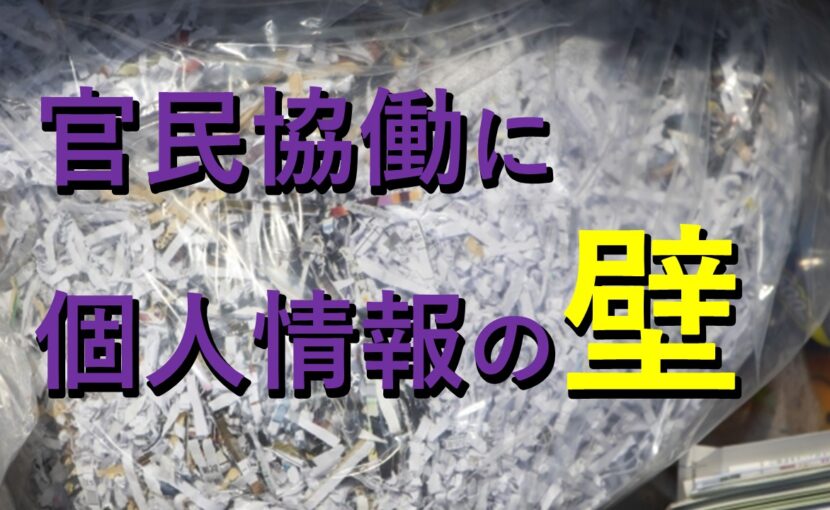

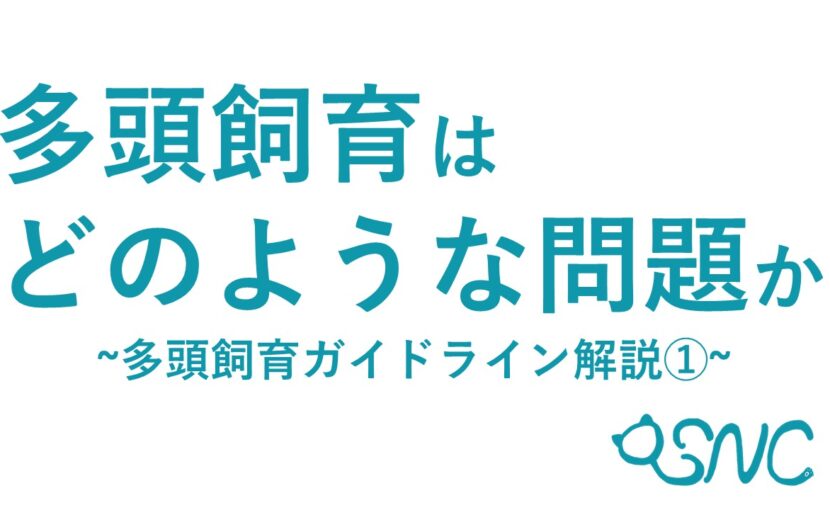
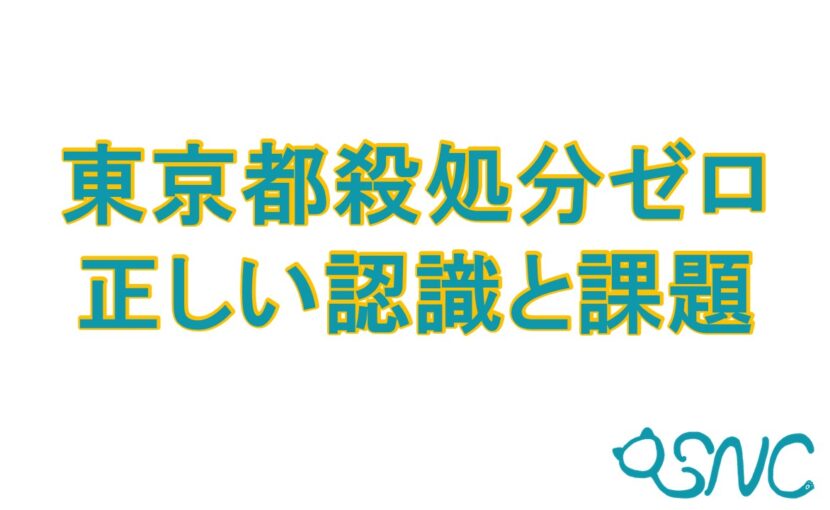
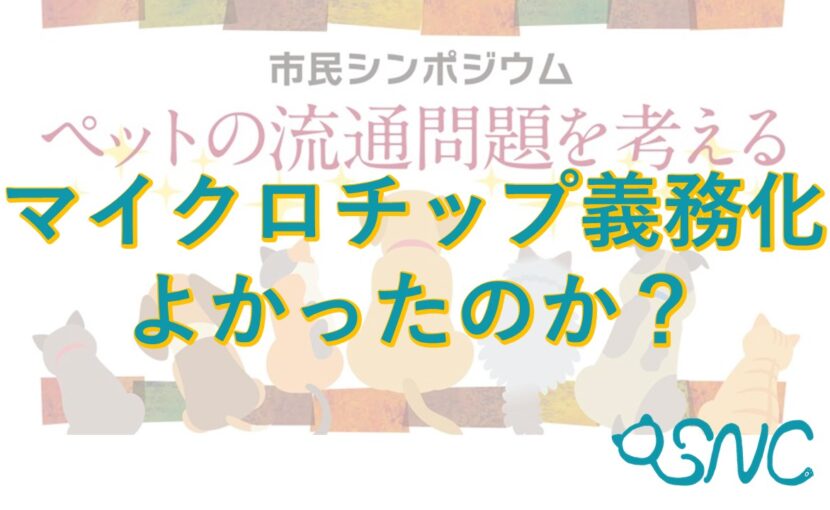
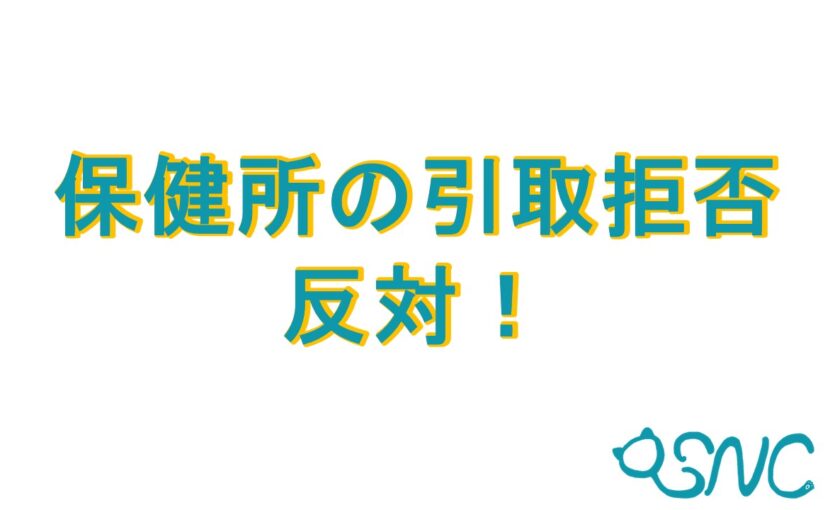
この記事へのコメントはありません。